(かばん):標の想いの欠片
(かばん):オフィーリアの育てた黒薔薇
装備枠(首):337ふぁいあのチカチカ蝋燭
装備枠(右手):[手]面影の一欠片
装備枠(左手):[手]冥界人形ヴィオレッタの鳥籠
(かばん):オフィーリアの育てた黒薔薇
装備枠(首):337ふぁいあのチカチカ蝋燭
装備枠(右手):[手]面影の一欠片
装備枠(左手):[手]冥界人形ヴィオレッタの鳥籠
アイリが残した紙切れ
「まつろう影が振り返るはずもなく。 後ろに佇む姿かたちなど捉えられるわけもなく」
「掲げたはずの星も見えず、立ち込める暗闇は悪夢への階のよう」
「やがて朝が来る。 夜の終わりを告げに、白い陽が昇る」
「僕がついて行けるのはここまで。 尤も、そんなことわかっているだろうがね」
長い尾を揺らすように、暗がりに佇む"それ"は不意に笑みをたたえる。
眩しいばかりの暁光を鬱陶しく思うように細めた双眸さえも、あたかもそう彩られたように思えた。
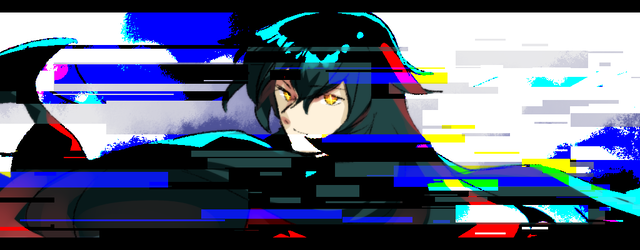
「天上の星など見えなくとも、君が抱いた夢は消え失せなどしない」
「叶えたい夢は叶ったかい。 それとも、新しい望みでも見つけたかい?」

「君ならばいっとう、本質的に──僕のようなものを忌避するだろう」
「構わないさ。 君が無我夢中にでも真直ぐ突き進もうとするように、僕が僕であるように」

「近しくて遠い隣人へ。 望むものは多かれど、好きに生きる今の実りさえあればいい」
「いつかいつかの日への望みを開花させるために。 ただ蹲るように、そこに留まりながら」

「やがて散華するとしても、それだけが唯一の望みなのだから」
「そこに後悔などありもしないだろう。 たとえ希望が見えなくとも」
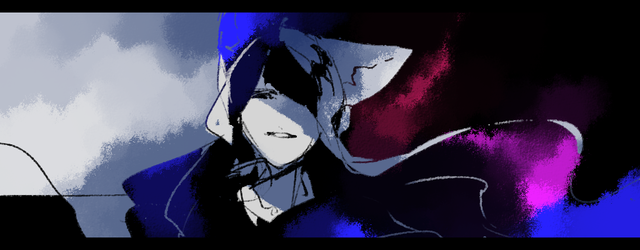
「夢の傀儡に、追わねばならぬ星など見えるはずもないんだよ」
「命運など信ずることもない。 眼前に広がる景色だけが現実なのだから」
「自由で、奔放で。 行きつく果ても見えない。 それだけが、確かに望んだ世界だ」
寂しさを伴わせるような沈んだ声色で、淡々と語るように"それ"は云う。
彼が暗闇へと向き直れば、そこには燦然と瞬く光がひとつあった。そうして、
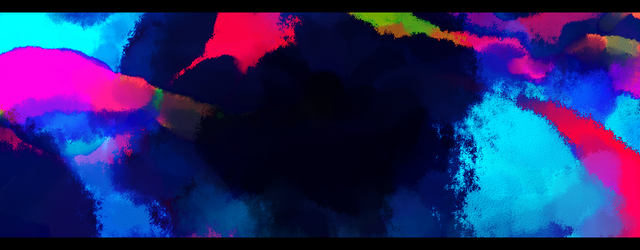
「──君にはどんな景色に見えている?」
「答えなくとも構わないさ。 興味本位だよ」
「ただ。 願わくば、」
"それ"は、__男は、額縁に手をかけるようにゆっくりと暗がりに触れる。
身もよだつような蟠る闇夜のただなかに、意識が囚われんばかりの光が降り注いだ。
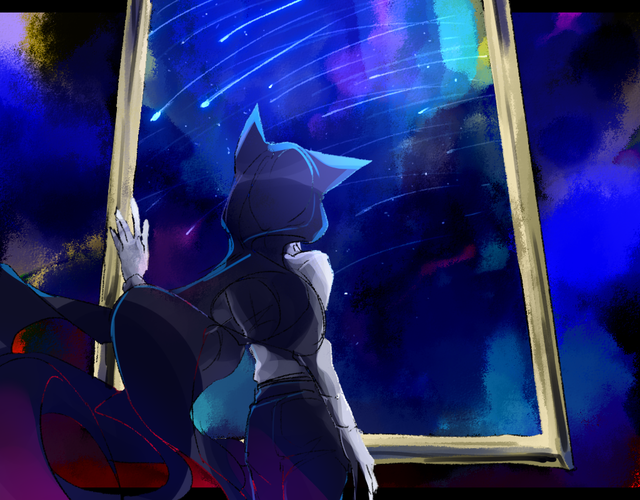
「振り返ることのなくなった、──いつかの憧憬がそこにあればいい、と」
「そう思うらしい。」
黒猫が一匹、鳴いている。
廃れたアトリエに人影などあるはずもなく、ただ溢れんばかりの陽光が景色を照らし出した。
乾いた絵のパレット。がらんどうの額縁。打ち捨てられた絵筆。
忘れ去られたようなそれらは、ただあるべき場所で眠りに就いている。
「猫も杓子も、征くべき先にいきつくだろう」
「夢の最果てへ。 そうあれと、そう望んだのだから」
「まつろう影が振り返るはずもなく。 後ろに佇む姿かたちなど捉えられるわけもなく」
「掲げたはずの星も見えず、立ち込める暗闇は悪夢への階のよう」
「やがて朝が来る。 夜の終わりを告げに、白い陽が昇る」
「僕がついて行けるのはここまで。 尤も、そんなことわかっているだろうがね」
長い尾を揺らすように、暗がりに佇む"それ"は不意に笑みをたたえる。
眩しいばかりの暁光を鬱陶しく思うように細めた双眸さえも、あたかもそう彩られたように思えた。
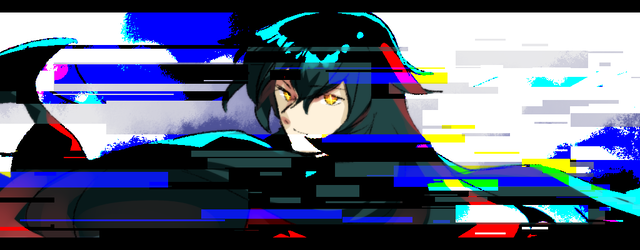
「天上の星など見えなくとも、君が抱いた夢は消え失せなどしない」
「叶えたい夢は叶ったかい。 それとも、新しい望みでも見つけたかい?」

「君ならばいっとう、本質的に──僕のようなものを忌避するだろう」
「構わないさ。 君が無我夢中にでも真直ぐ突き進もうとするように、僕が僕であるように」

「近しくて遠い隣人へ。 望むものは多かれど、好きに生きる今の実りさえあればいい」
「いつかいつかの日への望みを開花させるために。 ただ蹲るように、そこに留まりながら」

「やがて散華するとしても、それだけが唯一の望みなのだから」
「そこに後悔などありもしないだろう。 たとえ希望が見えなくとも」
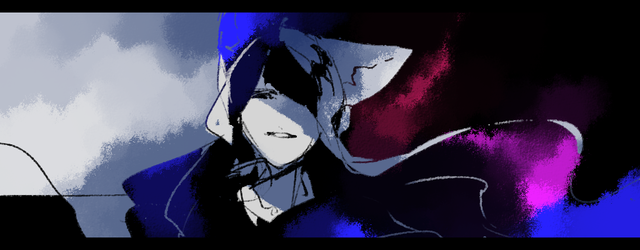
「夢の傀儡に、追わねばならぬ星など見えるはずもないんだよ」
「命運など信ずることもない。 眼前に広がる景色だけが現実なのだから」
「自由で、奔放で。 行きつく果ても見えない。 それだけが、確かに望んだ世界だ」
寂しさを伴わせるような沈んだ声色で、淡々と語るように"それ"は云う。
彼が暗闇へと向き直れば、そこには燦然と瞬く光がひとつあった。そうして、
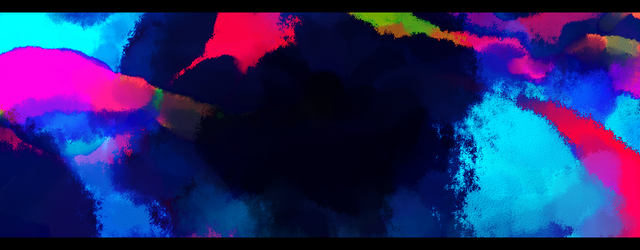
「──君にはどんな景色に見えている?」
「答えなくとも構わないさ。 興味本位だよ」
「ただ。 願わくば、」
"それ"は、__男は、額縁に手をかけるようにゆっくりと暗がりに触れる。
身もよだつような蟠る闇夜のただなかに、意識が囚われんばかりの光が降り注いだ。
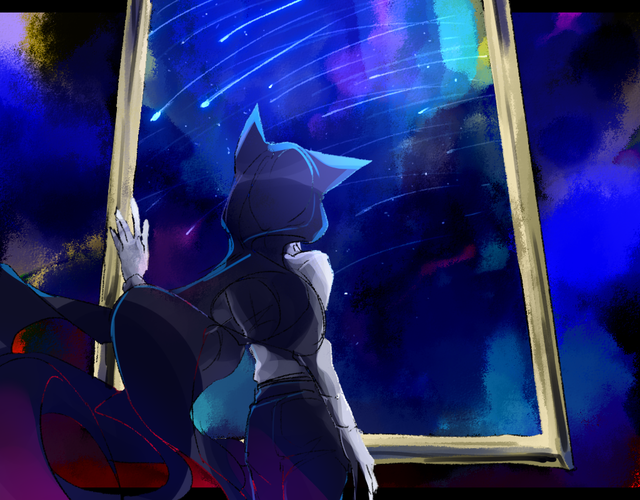
「振り返ることのなくなった、──いつかの憧憬がそこにあればいい、と」
「そう思うらしい。」
黒猫が一匹、鳴いている。
廃れたアトリエに人影などあるはずもなく、ただ溢れんばかりの陽光が景色を照らし出した。
乾いた絵のパレット。がらんどうの額縁。打ち捨てられた絵筆。
忘れ去られたようなそれらは、ただあるべき場所で眠りに就いている。
「猫も杓子も、征くべき先にいきつくだろう」
「夢の最果てへ。 そうあれと、そう望んだのだから」











